【開催レポート】学校教員向けセミナー「社会課題の解決を自分ごと化するには〜探究教材の活用と可能性」

株式会社大修館書店/NPO法人ETIC.
実行中
更新日:2022.11.30

2022年11月6日、株式会社大修館書店とNPO法人ETIC.の共催で、高校教員向けオンラインセミナーを開催しました。
タイトルは「社会課題の解決を自分ごと化するには―探究教材"社会課題解決中マップ"と"アクチュアル"~その活用の可能性」。社会課題解決中マップを監修する佐藤真久教授(東京都市大学)と、アクチュアル編集委員代表の米田謙三教諭(関西学院千里国際中等部・高等部)の二名にご登壇いただき、探究教材の活用による課題解決と価値共創の可能性についてお話しいただきました。
この記事では、当日ご参加できなかった学校教員の方々に向けて、セミナーの内容や探究教材の活用方法について要点をまとめてお伝えいたします。ぜひ参考にしていただき、授業にお役立ていただければ幸いです。
アクション詳細
目指す社会のあり方、ビジョン
複雑性に向き合い,学習と協働の連関を強めていく
貧困と格差、気候変動、少子高齢化、国際秩序の変化。ありとあらゆる社会課題が絡み合い複雑化が進む今、既存の枠組みに基づく対応では、もはや解決することができません。不確実性の高いこれからの社会において、私たちは常に状況的な判断を行い最適解を更新していくことが求められます。
このような試行錯誤の時代においては、チャレンジの経験の積み重ねそのものが極めて重要な意味を持ちます。これからの教育現場に求められるのは、あらかじめ正解が決まった教師主導の学びではなく、学習者自らが自分で学んでいこうという「自己主導型の学びと責任」ではないでしょうか。
その中で重要なことは、学習者自身の「内発的な動機付け」です。つまり心がワクワクドキドキするような“遊び”こそが一人ひとりの学びの源泉となります。実体験を伴った興味関心があれば、それは次なる行動を起こす情熱につながるでしょう。いかにして社会課題を自分ごと化させ、社会参画につなげていくのかということが、これからの教育においてますます求められる重要な視点です。
アクションリーダー プロフィール
-
 佐藤真久/米田謙三
佐藤真久/米田謙三
-
佐藤真久/東京都市大学大学院環境情報学研究科 教授
英国国立サルフォード大学にてPh.D.取得。地球環境戦略研究機関(IGES)、ユネスコ・アジア文化センター(ACCU)を経て現職。現在、UNESCO ESD-Net 2030 フォーカルポイント、JICA教師海外研修(SDGs)学術アドバイザー、文部科学省・WWLコンソーシアム構築支援事業運営指導委員、東京大学附属学校教育高度化・効果検証センター協力研究員、SEAMEO-JAPAN ESDアワード 国際審査委員会委員、などを務める。ETIC.理事等を歴任。協働ガバナンス、社会的学習、中間支援機能などの地域マネジメント、組織論、学習・教育論の連関に関する研究と実践を進めている。
米田謙三/関西学院千里国際中等部・高等部 教諭
社会科・総合探究科の科目を担当。文部科学省「高等学校学習指導要領解説 情報編」担当,経済産業省「未来の教室」STEAMライブラリーWG委員,総務省青少年の安心・安全なインターネット利用環境整備に関するタスクフォース委員,内閣府他共催「高校生ICT Conference」実行委員長,日本英語検定協会派遣講師などを兼任。大修館書店"アクチュアル"編集委員代表。
団体/企業詳細
- 団体名
-
- 株式会社大修館書店/NPO法人ETIC.
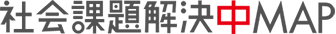
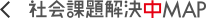 に戻る
に戻る




コメントを残す